2025年4月7日、日経平均が一時2,900円下落するなど大幅な下落が発生しました。投資している人達は阿鼻叫喚の状況となっています。
私自身も、含み損が10万円を超える等なかなか厳しい状況となっています。
しかし、株式市場の歴史において大幅な下落があったのは、今回だけではありません。
今回は株価暴落の歴史について紹介し、それに併せて暴落時の対応について私個人の対応方法を紹介します。
株式の歴史
まずは株式はそもそもどのようにして始まったのかという点ですが、事は13~14世紀のヨーロッパから始まっています。
株式の始まり
13〜14世紀ごろ:イタリアの商人たち
- イタリアの都市国家(例:ヴェネツィア)では、大航海や貿易を行うための資金を集める手段として、出資という形が生まれました。
- 投資家が航海に資金を出して、その見返りに利益の一部を受け取るという仕組み。これは株式の原型といえます。
株式会社の誕生
1602年:世界初の株式会社「オランダ東インド会社」
- オランダで設立された「オランダ東インド会社(VOC)」が、世界で初めて株式を発行。
- 投資家たちは株を購入し、会社の利益の一部(配当)を受け取ることができました。
- 株式はアムステルダム証券取引所で売買され、株式市場の誕生となります。
その後の発展
18〜19世紀:イギリス・アメリカで拡大
- 産業革命で大量の資金が必要になると、企業が株式を使って資金を集める手段が急速に広まりました。
- ロンドン証券取引所(1801年)や、ニューヨーク証券取引所(1792年)などもこの時期に発展。
- 多くの鉄道会社や工場が株式によって資金調達を行いました。
現代の株式制度
- 現代の株式会社制度は、投資家が株主として会社の所有権の一部を持ち、経営に影響を与える権利を持つ形に整理されています。
- 株式市場は世界中に存在し、資本主義経済の柱の一つとなっています。
まとめると・・・
| 時代 | 出来事 |
|---|---|
| 中世 | 商人たちの出資制度(航海投資など) |
| 1602年 | オランダ東インド会社が世界初の株式を発行 |
| 18〜19世紀 | 産業革命により株式制度が拡大 |
| 現代 | 株式市場は国際的に整備され、個人投資家も参加可能に |
このように、株式は長い歴史の中で資本主義の根幹となっており、現在の資本主義の要となっています。
株価暴落の歴史
ここからは株価暴落の歴史的な5つの出来事について、それぞれ背景や経緯など詳しく解説します。
1929年:世界恐慌(ウォール街の大暴落)
概要
1929年10月、アメリカ・ニューヨーク証券取引所で発生した大暴落は、世界的な大恐慌(グレート・ディプレッション)の引き金となりました。数日にわたる連続暴落により、株価は急落し、多くの投資家が破産に追い込まれました。
背景
1920年代は「狂騒の20年代(Roaring Twenties)」と呼ばれ、アメリカでは経済成長と株式ブームが起こっていました。
多くの人が証券を担保に借金をして株を買い、信用取引が加熱。実体経済とかけ離れた株価水準になっていました。そこへ金利引き上げや景気減速の兆しが現れたことで、一気に投資家の不安が高まりました。
経緯
- 1929年10月24日(ブラックサーズデー):株価が急落しパニック売りが始まる。
- 10月29日(ブラックチューズデー):売りが売りを呼び、株価は壊滅的な下げに。
影響
- アメリカ経済は壊滅的打撃を受け、銀行の大量破綻、企業倒産、失業率急増(25%超)に。
- 世界中に恐慌が波及。特にドイツなど第一次大戦後の復興途中の国々には深刻な影響。
- 金本位制の崩壊、保護主義の強化、ナチスの台頭など、後の世界大戦の原因の一端にも。
1987年:ブラックマンデー
概要
1987年10月19日(月曜日)に発生したこの暴落は、ダウ平均株価が1日で22.6%も下落した、米国株市場史上最悪の1日として知られています。
背景
- 1980年代前半の景気回復を受け、株価は好調に推移。
- 株価が過熱する中で、機械的な「プログラム売買(コンピュータによる自動売買)」が急増。
- 米国の貿易赤字、ドル高への懸念、利上げ観測などが重なって市場に不安が高まりました。
経緯
- 10月16日(金)に大きく下げた株価に不安が広がり、週明けの月曜日に売りが殺到。
- コンピュータによる自動的な売り注文が市場を増幅させ、記録的な暴落に。
影響
- 世界中の株式市場が連鎖的に下落。
- 金融システムへの不安が広がったが、比較的短期間で市場は回復。
- この経験から「サーキットブレーカー制度(取引一時停止制度)」が整備されました。
2000年:ITバブル崩壊(ドットコム・バブル)
概要
1990年代後半に急速に拡大したインターネット企業ブームが崩壊したのが2000年です。IT関連企業の株価は異常なまでに膨れ上がり、その後数年かけて大きく下落しました。
背景
- インターネット普及により「これからはITの時代」という期待が先行。
- ベンチャー企業が次々と上場し、利益を上げていないにも関わらず株価が急騰。
- 「.com」をつけた企業名であるだけで資金調達ができる状況に。
経緯
- 2000年3月、ナスダック総合指数が過去最高を記録(5048ポイント)。
- その後、企業の収益力が伴っていないことが明らかになり、失望売りが加速。
- 2002年にはナスダックが1100台にまで下落、ピークから約78%減少。
影響
- 多数のITスタートアップが倒産。AmazonやAppleなどの一部の企業だけが生き残る。
- 投資家心理が冷え込み、テクノロジー業界は長期にわたり低迷。
- その後、Google、Facebookなどが登場する新たなIT時代の土台に。
2008年:リーマンショック(世界金融危機)
概要
アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻したことを引き金に、世界中の金融市場が混乱した大規模な金融危機です。
背景
- 住宅価格の上昇を背景に、信用力の低い層向け住宅ローン(サブプライムローン)が急増。
- 金融機関はこれを証券化して売買(CDOなど)し、過大なリスクを抱えることに。
- 住宅バブルが崩壊し、不良債権が一気に顕在化。
経緯
- 2007年:サブプライム問題が表面化。
- 2008年9月15日:リーマン・ブラザーズが破綻。
- その後、AIGやメリルリンチなども経営危機に陥り、政府支援が続出。
影響
- 株式市場は大暴落。ダウ平均は1年で約35%下落。
- 多くの国で不況に突入、世界的な経済危機に。
- 各国は金融緩和政策、量的緩和(QE)を導入して危機に対応。
- バブルの後始末として「規制強化」「中央銀行の役割の再評価」が進む。
2020年:新型コロナウイルス・ショック
概要
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によるパンデミックが、経済活動を急停止させ、株式市場に大きな衝撃を与えました。
背景
- 2019年末に中国・武漢で発生したCOVID-19は、2020年初頭から世界中に拡大。
- 感染防止のため、各国でロックダウンや外出制限が実施され、経済活動がほぼ停止。
- 企業業績の急悪化、失業の急増、消費低迷などが一気に進行。
経緯
- 2020年2月下旬から3月にかけて、世界の株価は急落。
- ダウ平均は3月に20営業日で1万ドル超下落(約37%減)。
- VIX(恐怖指数)が過去最高を記録するほどのパニック相場に。
影響
- 株式市場の短期的な大暴落。
- 各国が前例のない金融・財政政策(ゼロ金利・給付金・金融緩和)を実施。
- 結果的に市場は急速に回復し、2020年後半にはコロナ前の水準を回復。
- テック株の爆発的成長、インフレと金利上昇という新たな課題も浮上。
株価暴落時の私なりの対応方法
ここまで株価暴落の歴史について紹介しましたが、長い歴史の中で浮き沈みがあって株価は成り立っているのが分かると思います。
裏を返せば、暴落した後には株価はまた回復して伸びているという事実があります。
私は旧NISA運用時にコロナショックにあい、投資していた株式が最大20万円近い含み損を抱えてしましましたが、その後1~2年で回復し、損を出さずに売買ができました。
そのため、長期的に運用をするのであれば、暴落にあっても持ち続けることで何とかなることが多いです。
短期的な暴落でパニックになる気持ちはよく理解できますが、冷静に判断し待ち続ける方法をとるのが今できることだと思っています。
株価暴落の歴史を振り返って対応を
今回は株価暴落の歴史と暴落時の私なりの対応について紹介いたしました。
暴落の歴史を知っておくことで、株価は浮き沈みを経て今の株価を形成しているということを理解していただけると幸いです。
冷静な判断をもって、この暴落の波を乗り越えられることを願っています。
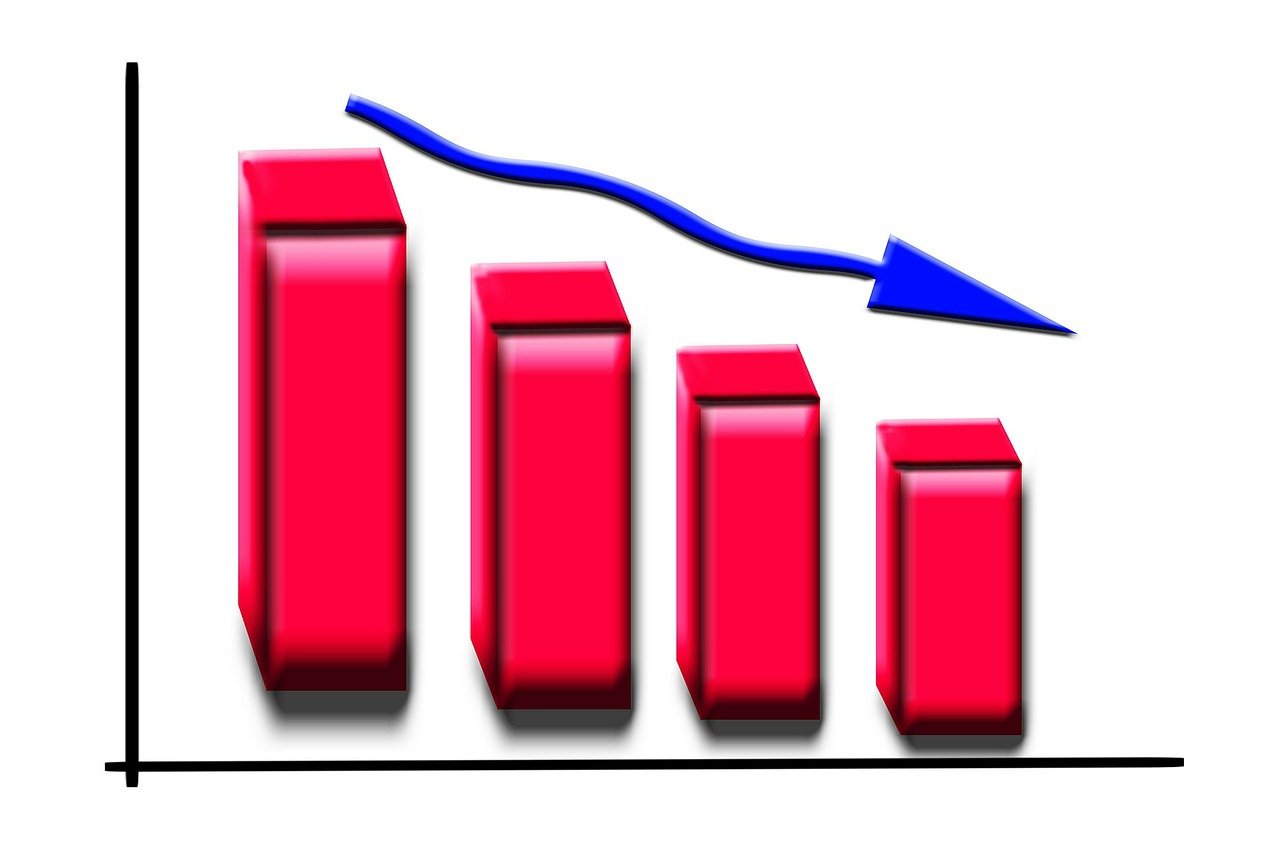





コメント