資産運用については、2024年の新NISA開始から興味を持つ方が増えていますが、どれだけの金額を運用に投じてよいのか分からないという人は多いと感じます。
運用をするにあたっては、その人のリスク許容度に基づいて投資していく必要があります。
今回はまずリスク許容度について解説したのち、20代、30代、40代、50代以降の4つの年代に分けておすすめの投資スタイルを紹介したいと思います。
リスク許容度についてとその強度
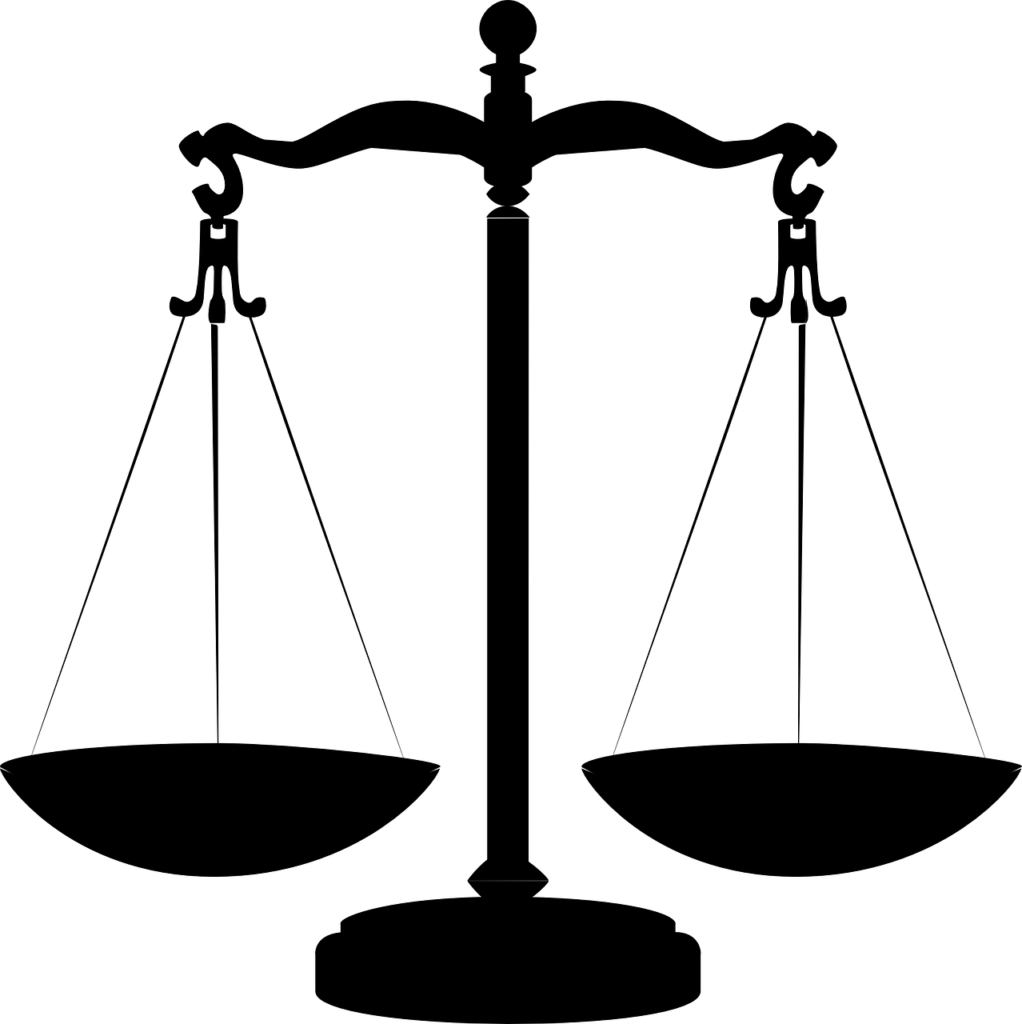
資産運用についてのリスク許容度とは、「どれだけなら投資に投じても問題ない」というのを比較的に示したものです。
リスク許容度は個人差が大きくあります。それぞれ比較していくと、
- 既婚・子持ちよりも独身の方がリスク許容度は高い
- 若い方がリスク許容度は高い
- 投資の勉強をしている方がリスク許容度は高い
といった形で比較する許容度です。
例えば、20代の独身で投資の勉強をしている方はリスク許容度は高く、多額の投資に向いていますが、50代の既婚・子持ちである場合はリスク許容度は低くなり、多額の投資はあまり向いていないといえます。
「投資にかけたお金をどこまでなら失っても大丈夫」という認識がリスク許容度といってもいいでしょう。
実際に数値化されるものではありませんが、体感として理解してもらえればと思います。
各年代別資産運用策について
ここからは、年代をリスク許容度の尺度として、各資産運用策について紹介します。なお、あくまでも年代別であり、参考程度に考えてもらえたらと思います。
20代からの場合
20代からであれば、リスク許容度は高いため、様々な投資にチャレンジしてもよいと思います。ただ、ある程度は投資について勉強をしておくとなお良いでしょう。
若い年代であれば、個別株にチャレンジしてもいいですし、手堅い投資信託に時間をかけて育てていくのも悪い選択ではないです。
投資商品と現金の比率としては、攻めるのであれば投資商品80%を目標にしつつ、生活資金を上手く切り詰めていく形となります。
他に趣味を楽しむスタイルであれば、投資50~70:現金50~30程度を考慮していきましょう。
30代からの場合
30代からの場合は、多少リスク許容度は低くなりますが、ある程度の投資には挑戦できます。知識を身に着けていれば、挑戦の幅は広がるでしょう。
独身の場合は、20代と比率の大差はなく、攻めたポートフォリオを形成してもよいかと思います。ただ、既婚の場合は少し比率を現金に寄せる必要があります。
投資の勉強をしていた方は、この年代に始める方も多い分、長期的な投資信託も十分効果を発揮すると思います。
40代からの場合
40代からの場合だと、大半の方は既婚となることが多く、年代としてもリスク許容度は低くなってきます。
生活に必要な資金も増えるため、投資商品は全資産の50%が捻出できる限界と思う方も多いです。生活資金が多い場合は、無理をせず投資信託に積み立てするぐらいで考えてもよいと思います。
この年代からどうしても投資に費やす資金が捻出しにくくなりますので、それがリスク許容度だと考えてください。
投資信託の場合は、ここから20~30年積み立てするだけでも成果はでやすいので、積み立ては可能な限り行っていきましょう。
50代以降からの場合
50代以降からの場合だと、複利効果を生かすにも時間的な制約も多くなります。リスク許容度も低いため、大きな投資はしづらいといえます。
リスク許容度は低い方が多いため、思い切った投資は避けることをおすすめします。特に退職金が出る年代は、退職金を使って不慣れな大規模投資をして、失敗することが非常に多いので注意したほうがよいでしょう。
この年代はできるだけ現金を保有する方向で、投資信託を積み立てていく方針が無難です。貯金をしている方は、月1~2万円程度の積み立てでもOKです。
リスク許容度が低い分、利益を出しにくくなってしまいますが、リスクとリターンは表裏一体なので、知識がある方以外はおすすめできないです。
資産運用とリスク許容度についてのまとめ
今回は資産運用とリスク許容度について、年代別の方針を紹介いたしました。
自分自身のリスク許容度を正しく理解することで、投資に対して焦りや後悔といった感情が発生しにくくなります。
投資を行う際はこのリスク許容度を常に意識しておき、適切なリスクをとって利益をだしていきましょう。






コメント